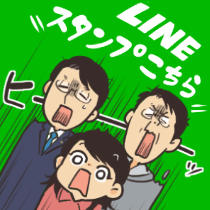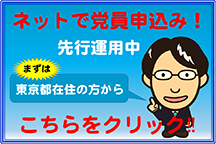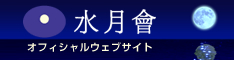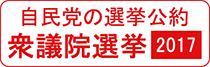■ ブログ:永田町日記
-
2006年4月15日 02:51
7年後に商工中金も民営化されることになった。今から5,6年前、貸し渋り貸し剥がしの嵐が吹き荒れ、民間銀行が足並みそろえて逃げ出すなか、商工中金は中小企業金融の使命を果たすために逃げずに踏み止まり、多くの中小企業を救った。中小企業に対する貸し出しがこの金融機関のIDENTITYであり、刻み込まれた使命だからである。商工中金の民営化後の姿を検討していくなかで、多様なサービスを取り扱い、収益性を高めると言う議論もあるようだが、私は反対だ。むしろ逆に中小企業のための銀行というDNAをきっちりと引き継いだ銀行にすべきである。そうでなければその他のたくさんの銀行と全く代わり映えのしない銀行がただひとつ増えるだけの話だ。「官」から「民」への構造改革の流れの中で、「官」は「民」の補完に徹するべきだという大原則だが、中小企業金融の場合、社会的責任の自覚もなく真っ先に逃げ出す連中を、どのように補完することができるのだろうか。また、不良債権処理がひと段落ついた大銀行は中小企業への貸し出しを伸ばしているというが、いつまた豹変するのか、全く信用できない。つい最近の三井住友銀行の中小企業融資と金利スワップ商品の抱き合わせ(公取から排除命令)を見れば、大銀行のカルチャーは全く変わっていないと思えてならない。私は自民党の部会などで、商工中金の民営化には反対しないが、その理念や使命を引く継ぐための根拠法が必要だ(例えばNTTやJRのような)と主張し続けてきた。今後の民営化後の具体的な機能や組織作りの局面で積極的に発言をしていく。
また先の特別国会で銀行法が改正され、一般事業会社の銀行代理店業務が解禁される。例外的にという形で事業性融資も取り扱う方向になったが、地域金融機関への配慮からか、貸出上限金額はあまり高額にはならないよう、1000万円程度を想定しているようだ。中小企業の側から見れば、とにかく選択肢が多いことが重要であり、選択肢に成り得るにはせめて5000万円位の上限金額が必要ではないかと考える。
中小企業金融の世界での構造改革とは、官から民への転換と言うよりは、貸し手本位から借り手本位への転換ではないか。今までの金太郎飴のような画一のサービスしか存在してこなかった金融環境から、個性豊かなサービスを競う金融機関がたくさん存在し、借り手の側が選択し、組み合わせて利用していくという新しい金融環境への転換である。ひとつの地域に、商工中金のような使命のはっきりした銀行があり、モニタリングを重視した地元の信金・信組があり、スコアリングモデルを駆使した大手銀行の代理店がある。そして、中小企業の経営者は自らの企業の信用状況や、新規に取り組む事業の収益性を勘案し、自己の責任において選択し組み立てていく。衆議院の委員会で私が質問をすると、商工中金の件は経産省、銀行代理店の件は金融庁の答弁となるが、中小企業の側に立って、関連する役所が先に述べたような中小企業金融のあるべき姿といったビジョンを共有し、一体的に取り組むことが重要である。
HPアドレス http://www.taira-m.jp/